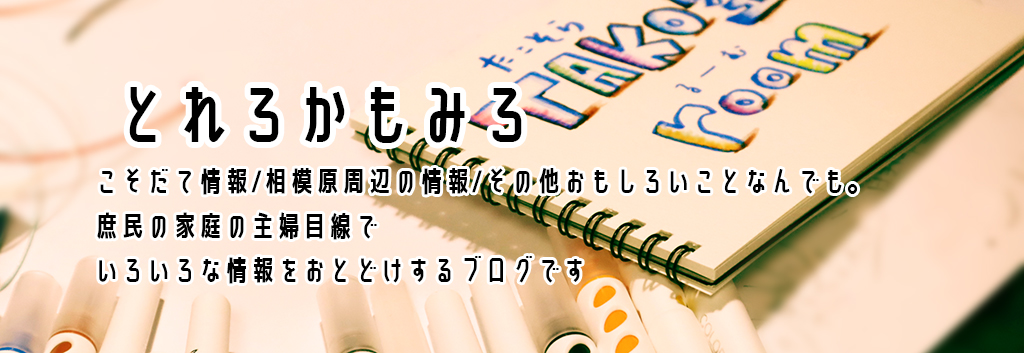【はじめに】
※この記事は書籍を紹介する内容です。当方は著作権を侵害する目的ではこの記事を書いておりませんが、もし何らかの問題を発見された際には是非お問い合わせフォームよりご連絡を頂ければ幸いです。直ちに対応させていただきます。
こんにちは!さがみはらのママブロガーTAKOです♪
今日のテーマは「書籍」です!

衝撃のタイトルの本を見つけてしまって購入しないわけにいかなかったんですよ。
これです。
じゃん。

え?どゆこと?(目ェコスリコスリ・・・二度見・・・・)(゚Д゚;)
い、いちにち・・・?1日だと・・・?
しかも概要を読むと薬いらずで花粉症が治るというような話。
(最近はYouTubeのさまざまな書籍紹介チャンネルさんでも取り上げられていますので、知っている方は多いですよねきっと)
とにかくこれ買ってみよう!
嘘かもしれないけど!
読んでみて、実践して本当に花粉症が治ったら真面目にこの本の著者さんを神とあがめてしまうかもしれない。
それくらいに私・私の娘は花粉症に悩まされています。

毎年2月ころには目がかゆく・鼻もジュルジュル。
コロナのずっと前から春はマスク必須の人生。
目薬・飲み薬・鼻シュッシュ・・・
この時期はいろんな抗アレルギー薬を携えて出かけねばならずそれを忘れたときの絶望感と言ったらもう・・・・(´;ω;`)
「薬なしで花粉症を克服できないのか?!」
TVでは、「花粉が飛び始めました!」とか
「花粉症の薬はこれがいいよ!」みたいな事についてはジャンジャン教えてくれる。
だって、薬売れて儲かる方がいいもんね。みんな。
薬なしで花粉症を克服する方法なんて誰も教えてくれなかった。
藁をもすがる思いで手にしたこの一冊。
本の通りに実践中の我が家の生活を少しばかり紹介いたします。
誰かの何かに役立てば幸いです。
興味をお持ちの方はこの先をどうぞご覧ください。
結論から言っちゃうと
著者が言いたいことはひとつでした。
前書きからもうバッチリ結論を述べてます。
本の宣伝でも既にこの結論は書かれていまして、ネタバレしても良さそう。
結論とは・・
「フラクトオリゴ糖」を摂りましょう
ってことみたいです。
書籍のタイトル「花粉症」って書いてあるので
花粉症だけが治るのかと思ったんですがそうじゃ無いみたいです。
花粉症以外の様々なアレルギー・アトピー・うつ・不眠など
様々な体の不調が改善するとのこと。
書籍のタイトルはキャッチーにするためにあえて
「花粉症」だけを入れたのかも。
なぜフラクトオリゴ糖がそんなにイイの?
って、もっと詳しく知りたい方は是非書籍を読んでみてください。
読むとなぜフラクトオリゴ糖がそこまで大切なのか解説されています。
amazonに記載されている書籍紹介を引用すると下記の通りです。
アレルギー研究の世界的権威が、医者に治せない免疫疾患の改善にズバリ答えを出す!
amazon 「花粉症は1日で治る!」紹介ページより引用 https://amzn.to/3vJcJgh
その鍵は……「酪酸菌」と「フラクトオリゴ糖」!
「フラクトオリゴ糖」を1日に10g以上摂る
↓
「酪酸菌」が増える
↓
あらゆる炎症が抑えられ、花粉症はもちろんアレルギーの9割、うつ、不眠が1日で改善する!
フラクトオリゴ糖ってどうやってとればいいの?
難しいことは分からない。
でもとりあえずフラクトオリゴ糖ってやつをとればいいんだね!OK!
でもどうやって摂るの?・・・
ごぼうを毎日1本

書籍の中で著者はなんと
「ゴボウを食べれば間違いなく花粉症は治る」
と断言しています。
書籍内でも紹介されていますが
「ゴボウを毎日1本分食べれば必要なフラクトオリゴ糖がとれる」とのことなのです。
実践!
「ゴボウを毎日食べる」
簡単なようで、とても厳しい!
私は働くママなので、料理にいつもそこまで手間がかけられません・・・(゚Д゚;)
スーパーで売っているゴボウサラダはどうだろう???
これなら袋から出すだけで食べられるし、こどもも大好きだし良いかも!
料理が好きだったり、時間をかけられる方なら
ゴボウをスーパーでまとめ買いして味噌汁に入れたり、煮物にしたり、サラダにしたり、意外とイロイロな料理で使えるので、それが一番コスパはいいかも。
【余談】ごぼうのレシピ紹介
味の素のHPでは材料別でレシピを検索出来たり便利でおススメです。
例えばゴボウで検索すると・・・

このようにゴボウを使ったレシピが出てきます。
他レシピサイトは素人の作ったメニューとか、奇をてらったメニューが多く並ぶことが在るけれど、味の素は割と一般的なメニューが並ぶのでおススメです。
ゴボウのポタージュなんて子どもでも食べやすそう。
今度作ってみよう。

フラクトオリゴ糖はamazonでも買える
料理でもなるべく摂り入れよう!!
とは思ったものの。
そんなフラクトオリゴ糖をゴボウから摂取できる自信がない・・・
と思ったので、amazonでとりあえずフラクトオリゴ糖を購入してみました。
粉末タイプと液状タイプどっちがいい?
粉末タイプ
購入して使用してみましたが、粉末タイプの方は「ブラウニーの上にかかってる粉糖」くらいに粒子が細かいので湿気で固まる恐れがあります。外に出して置いておくのは厳禁です!
開封したら冷蔵庫で常に保管しましょう!!
細くて長めのスプーンを袋の中に常に突っ込んでおいて、使いたいときはスプーンですくって食べ物や飲み物に入れています。
お湯なら簡単に溶けるのですが水には溶けにくいです。
(水に入れるとスライムのようにドロッとした何かに変わっていつまでも残る)
ホットドリンクやヨーグルトなどに混ぜるのには有効かなと思います。
液状タイプ
フラクトオリゴ糖の液状タイプもあります。
冷たい飲み物にも溶けやすいのと、常温で固まることもないので粉よりも扱いやすいです。
↑大容量タイプもあります。レビューには「でかすぎる」という意見もアリ。
スーパーなどでも売っているところはあるみたいですがフラクトオリゴ糖ではないオリゴ糖の場合もあるので、間違えやすく注意が必要です。
しばらく使ってみた感想ですが、粉末タイプよりも甘味が強いように感じます(商品によって甘さは変わることもあるかも?)。もし甘いのが好きならこっちの方がイイかもです。
長沢オリゴ

上で紹介したフラクトオリゴ糖でももちろん良いと思いますが
著者の小柳津広志先生が公式に運営しているカフェで販売されているフラクトオリゴ糖があります。
「長沢オリゴ」です。
少しamazonのモノと比べると割高感がありますが、著者が直接関わって作られているという信頼感もあります。
通販でも購入可能なようなので、試してみたい場合は是非どうぞ!
我が家のフラクトオリゴ糖の楽しみ方
・プレーンヨーグルトに好きなジャムとフラクトオリゴ糖スプーン一杯入れて食べる
・無糖のホットドリンクに甘味料として入れる
・カレーでも味噌汁でも。食事を作るとき、とにかく混ぜてみる
・究極・そのまま舐める
とにかく毎日何かしらのフラクトオリゴ糖を摂取する生活をしています。
あとは出来るだけゴボウを食べる機会があるときには積極的に摂っています。
これなら美味しいし、めちゃ楽なので、何の苦労もなく続けられそう。
[疑問]フラクトオリゴ糖って熱湯で溶かしてもいいの?
よくビタミンとかの話で、栄養素が熱によって壊れるとか聞くことがあるので、「フラクトオリゴ糖」は加熱しても大丈夫なのかな?と疑問に思いました。
結論から言うと「フラクトオリゴ糖は熱湯で溶かしてダイジョブ」です。
オリゴ糖は熱に強いです(160℃までOK)。
味噌汁・煮物など通常の料理なら大丈夫。
ただし、ジャムなど長時間酸性下で過熱するのは効果が落ちるコトがありNGのようです。
詳しくは日本オリゴ公式HPをご覧ください

気づいた注意点
類似品が多い!
「オリゴ糖」ならなんでもいいのかな?
・・と思って買っちゃうのはちょっと待ってください。
ちゃんと「フラクトオリゴ糖」って書いてある商品・しかも他の甘味料(ブドウ糖・果糖)がなるべく混ざっていない商品にしましょう。製品の原材料名を確認すれば余計なモノが入っていないかが分かります。(書籍の中でもその点については注意喚起されています)。
おなかがゆるくなる人がいる
人によっては「フラクトオリゴ糖」でおなかがゆるくなる方がいらっしゃるそうです。我が家は比較的大丈夫なのですが、食べ過ぎ厳禁。少しづつ様子を見ながら摂取するのがおススメです。
甘味はそんなにない
フラクトオリゴ糖にそんなに甘さが無いのと一日の使用目安もあるので砂糖の代用としては使用できないと思います。他の甘味料(蜂蜜など)と併用したらいいかな?とは思います。
逆にその甘味の無さが甘さが苦手な人にとってはメリットになるかも。
特に粉末タイプは甘さがそんなに無いので、甘くない方がいい方は粉末タイプをおススメします。
「酪酸菌」を直接サプリで摂取するのはダメなの?
「フラクトオリゴ糖をエサにして酪酸菌が増える」
とのことなので、酪酸菌サプリで直接摂るのはだめなのかな?と思いました。
世間では酪酸菌のサプリというのが市販されています。
まず代表的なのが「強ミヤリサン錠」
入っているのは酪酸菌(宮入菌)だけという潔さ。
もう一つ代表的なのが、「ビオスリーHi」です。
こちらは酪酸菌/糖化菌/乳酸菌が配合されたものです。
こちらはかなりメジャーなので、ほとんどの薬局で置いてあります。手に入りやすさは一番かもしれない。
あとはツルハドラッグのプライベートブランドになりますが
ミヤフローラEXというサプリもあります。
上の「強ミヤリサン」と同じ会社が作っていますが、中身は「酪酸菌」と「ウルソデオキシコール酸」が含まれています。
サプリで摂ることの効果は人によるとのこと。
腸内環境は人それぞれ、全然違うので整腸剤が合う合わないがあるからです。
もし試してみたい場合は即効性はないので、最低でも1か月は飲み続けて自分のおなかの調子がどうなったか。よく観察してみてください。
ただ、著者曰く酪酸菌は日本人のおなかの中にすでに持っているものなので菌の餌になるフラクトオリゴ糖(ゴボウなど)を毎日取れば自然に酪酸菌は増えていく。という説明でした。
つまり、「サプリに頼らなくても日々の食生活でどうにかなるよ。」
ということを著者は言っているのだと思います。
【おまけ】花粉症を抑えるためには!!一覧!
フラクトオリゴ糖以外にも薬なるべくナシで花粉症を抑えるにはこうするとイイかも。ってものがあったりするのでそれを自分なりに調べてみました。
※効果については人それぞれですので、ご自身で試して確認してみて良いものを取り入れてみてください。
【NG!】摂取するのを控えるべきもの××
アルコール ×
アセトアルデヒドがアレルギーを引き起こすヒスタミンの放出を促す。
血流が良くなりすぎてかゆみが出たりしやすくなる。
香辛料 ×
アレルギー反応を促進させる恐れあり
脂肪の多い食べ物 ×
脂身の多い肉・揚げ物など
悪玉菌を増やす
小麦 ×
小麦に含まれるグルテンがリーキーガットの原因。
イネ科なのでアレルギーを悪化させる恐れ。
砂糖 ×
アレルギーに対抗するホルモン分泌を減少させる
トマト・メロン・スイカ ×
花粉症の原因となるアレルゲンと似たたんぱく質が含まれている。
季節で考えるとメロンやスイカはそんなに食べる機会はないかも?
摂取したほうがいいもの
乳酸菌
砂糖はなるべく添加されていないものを選ぶ。
ヨーグルトやチーズ、味噌、キムチなどの発酵食品も乳酸菌。
食物繊維
きのこ類、ゴボウ、海藻、レンコンなど。
乳酸菌などの善玉菌のエサになる。
高カカオチョコ
カカオポリフェノールが有効
青魚
DHA(ドコサヘキサエン酸)・EPA(エイコサペンタエン酸)が有効
緑茶
ヒスタミンの働きを抑えると考えられているカテキンが有効
甜茶
甜茶ポリフェノールが有効。甜葉懸鈎子100%の甜茶を選ぶ
ルイボスティ
フラボノイドが有効。ノンカフェイン。
コーヒー
クロロゲン酸が有効。

※これらは摂ったからと言って急に花粉症が改善するわけではなく、大量に取るのではなく毎日少しずつ摂ることが推奨されています。日々の食生活にこういったものを摂り入れつつ、規則正しい生活・暴飲暴食をやめるといった基本的なリズムを大事にするのが前提となります。
その他・花粉対策に効果的なもの
アロマオイルを活用する
ユーカリ・ティーツリー・ペパーミントなど
※妊娠中の方は取扱い注意
TAKOが現在使用しているアロマディフューザー。おススメです♪(*’▽’)
【追記】TAKOの花粉症報告(2023年2月時点)
上記のように腸内環境に気を付けながら生活をしてしばらく経ちました。
ゴボウを摂れるときには食べ、フラクトオリゴ糖を砂糖代わりに使い、小麦・砂糖・乳製品や脂肪分の摂取を減らし、代わりに野菜・果物の多い食生活を意識して過ごし・・・
現在2023年2月となりました。
花粉症の季節到来です。
さて。
TAKOの花粉症はどうなっているかの報告です。
去年の花粉症の出方より明らかに変わっているのが分かります。
確かにときどきくしゃみが出たり、目や、喉の奥がかゆくなったりすることがあるのですが、不思議なことに、しばらく待っているとそれは収まるのです。
目薬や飲み薬は今年は一度も使っていません。
「花粉症が治った!」とまでは思わないんですが、明らかに軽くはなっている。
と感じます。
私の場合「花粉症は1日で治る!」とはいかなかったです。
ただ、自分はこの本の通りゴボウ一本を1日に一回摂取するということはできず、できる限り。という感じでしたので、それをきちんと出来ていればもしかしたら今年の花粉症は完全に克服できていたかもしれません。
軽くなった!と言っても油断はできません。
三月になってからの方が花粉の飛散量が増えますので、その時期になったらどうなるのか?が分かりません。
効果は実感できるレベルにあるなぁと思います。
来年もっと軽くなっていてほしいからこの本をもっと熟読し、薬ナシで花粉症を克服できるよう努力してみたいと思います。
おわりに
今回は以上になります。
また経過をこちらの記事に追記していきながら効果の程を検証していきたいと思っています。
もし良かったら花粉シーズン終了ごろにまたこの記事に遊びに来て下さい。
最後までお読みいただきありがとうございました。
TAKO(*’▽’)
今回参考にさせていただいた書籍です。
大変読みやすいし、勉強になります。
是非興味ある方は読んでみてくださいね(*’▽’)
※今回の記事はすべての方に当てはまる内容ではありません。ご自身の体質などに合わせて多媒体の情報もキチンと調べた上で参考程度にとどめて頂ければ幸いです。